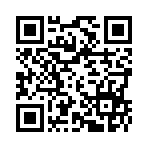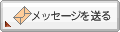2006年02月16日
赤瓦と漆喰と沖縄の風土
沖縄で最初に使われた瓦は、本土と同じような黒色系の瓦だったようです。
ではなぜ素焼きの赤瓦になったのか?
低温で焼きやすい、従って経済的という理由があります。
しかしここでは、風土の面から述べます。
沖縄では、代々受け継いだ家屋を強烈な台風から守るためには、漆喰瓦屋根が重要な役割を果たしました。
屋根に瓦をのせて荷重をかけ、その瓦を漆喰でつなぎ抑えつけることによって、家屋全体を強固にしていました。
本土の黒色系の瓦の品質で問題になるのは、瓦の吸水性だそうです。
瓦が素焼きのように水を吸いやすいと、冬の零度以下になる時期に、瓦に吸収された水分が凍結して瓦が割れることがあるそうです。それで、本土の瓦は吸水しにくい黒色系の瓦が主になるのだそうです。
しかしこうなると、黒色系の瓦は吸水しにくいため漆喰を塗り付けるのが難しくなってしまいます。
黒色系の瓦は漆喰がつきにくいのです。
本土の瓦をよく知ってるある建築業者さんが、「沖縄の瓦は水を吸いやすく、また漆喰を屋根に使っているからだめだ」というのを、聞いたことがあります。
それは、本土からみた視点であり、大きな誤解です。たしかに漆喰も吸水性が高いので本土では瓦屋根には使いづらいです。
しかし、ここ沖縄では時により2~3日も居座る猛烈な台風をしのぐには、漆喰で瓦を固定しないと屋根がもたないという、現実的問題があったのです。沖縄では冬でも水は凍りません。したがって凍結で瓦が割れたり、漆喰が劣化することはありません。
その漆喰が瓦にくっつきなじみやすいのが、素焼きの赤瓦だったのです。
私だって、特別に「赤瓦ばんざい!」という立場ではありません。黒色系の瓦のほうが耐久性は優れていますから。
ただ、漆喰塗りの赤瓦屋根が沖縄で発展したのは、特有の風土のもとそこにすむ人々の知恵の結集であることを理解してほしいのです。
ではなぜ素焼きの赤瓦になったのか?
低温で焼きやすい、従って経済的という理由があります。
しかしここでは、風土の面から述べます。
沖縄では、代々受け継いだ家屋を強烈な台風から守るためには、漆喰瓦屋根が重要な役割を果たしました。
屋根に瓦をのせて荷重をかけ、その瓦を漆喰でつなぎ抑えつけることによって、家屋全体を強固にしていました。
本土の黒色系の瓦の品質で問題になるのは、瓦の吸水性だそうです。
瓦が素焼きのように水を吸いやすいと、冬の零度以下になる時期に、瓦に吸収された水分が凍結して瓦が割れることがあるそうです。それで、本土の瓦は吸水しにくい黒色系の瓦が主になるのだそうです。
しかしこうなると、黒色系の瓦は吸水しにくいため漆喰を塗り付けるのが難しくなってしまいます。
黒色系の瓦は漆喰がつきにくいのです。
本土の瓦をよく知ってるある建築業者さんが、「沖縄の瓦は水を吸いやすく、また漆喰を屋根に使っているからだめだ」というのを、聞いたことがあります。
それは、本土からみた視点であり、大きな誤解です。たしかに漆喰も吸水性が高いので本土では瓦屋根には使いづらいです。
しかし、ここ沖縄では時により2~3日も居座る猛烈な台風をしのぐには、漆喰で瓦を固定しないと屋根がもたないという、現実的問題があったのです。沖縄では冬でも水は凍りません。したがって凍結で瓦が割れたり、漆喰が劣化することはありません。
その漆喰が瓦にくっつきなじみやすいのが、素焼きの赤瓦だったのです。
私だって、特別に「赤瓦ばんざい!」という立場ではありません。黒色系の瓦のほうが耐久性は優れていますから。
ただ、漆喰塗りの赤瓦屋根が沖縄で発展したのは、特有の風土のもとそこにすむ人々の知恵の結集であることを理解してほしいのです。
Posted by 瓦屋根 at 00:54│Comments(4)
│文化
この記事へのコメント
赤瓦といい漆喰といい沖縄の先人の知恵だったのですね。。。
最近、沖縄で木造建築や赤瓦屋根が見直されてきていますがまだまだですね。。。沖縄の風土にマッチングした建物が普及したらいいのにと思います。
最近、沖縄で木造建築や赤瓦屋根が見直されてきていますがまだまだですね。。。沖縄の風土にマッチングした建物が普及したらいいのにと思います。
Posted by pacific-18 at 2006年02月16日 10:12
pacific-18さん、たびたびコメントありがとうございます。
木造建築ができる大工は高齢になっているか、ほんとに少なくなりました。
建築物を、一代限りではない、100年単位の長い目で見通しのできる職人や、それを評価してくれるうちなーんちゅが増えてくれたらうれしいのですが。いまの建築物は消耗品的財産になってしまっています。
木造建築ができる大工は高齢になっているか、ほんとに少なくなりました。
建築物を、一代限りではない、100年単位の長い目で見通しのできる職人や、それを評価してくれるうちなーんちゅが増えてくれたらうれしいのですが。いまの建築物は消耗品的財産になってしまっています。
Posted by 瓦屋根 at 2006年02月16日 23:05
瓦屋根さん
はじめましてー!
足跡からきましたー。
時々遊びにきてくれてありがとうございます。
「沖縄の風土・文化」を理解せずして自分の感覚・尺度で
物事を批評・判断するのは幼い文化感覚だと思ってます。
瓦屋根さんの持論に大賛成ですー!
はじめましてー!
足跡からきましたー。
時々遊びにきてくれてありがとうございます。
「沖縄の風土・文化」を理解せずして自分の感覚・尺度で
物事を批評・判断するのは幼い文化感覚だと思ってます。
瓦屋根さんの持論に大賛成ですー!
Posted by 遊悠人 at 2006年02月17日 01:09
遊悠人さん、コメントありがとうございます。
私の話を読んでくださる方がいらっしゃって、実は少しほっとしています。
これからも、よろしくお願いします。
私の話を読んでくださる方がいらっしゃって、実は少しほっとしています。
これからも、よろしくお願いします。
Posted by 瓦屋根 at 2006年02月17日 22:57