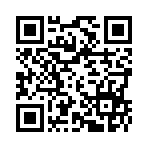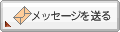2006年02月01日
本葺瓦と柳宗悦
漆喰シーサー(旧東風平町)

漆喰シーサー(那覇市)

柳宗悦は左官職人が作るシーサーにも祈りと美を感じ取り、さらにできばえの素晴らしいものには畏敬の念さえ持っていたようです。
「本葺瓦」と「柳宗悦(やなぎむねよし)」ってどういう関係があるんですか?
と、速攻で質問がきそうですが、まあせっかちにならないで、
すこしつきあって読んでください。
漆喰シーサー(那覇市)
柳宗悦は左官職人が作るシーサーにも祈りと美を感じ取り、さらにできばえの素晴らしいものには畏敬の念さえ持っていたようです。
「本葺瓦」と「柳宗悦(やなぎむねよし)」ってどういう関係があるんですか?
と、速攻で質問がきそうですが、まあせっかちにならないで、
すこしつきあって読んでください。
この仕事をとおして、たびたび悲しいというか非常に残念な思いにかられることがあります。
立派な木造赤瓦住宅に営業で漆喰塗り替えをお願いに伺うと、「検討する」と返事を頂きます。
しばらくして再訪するとその瓦屋根には既にペンキや防水塗装が施されているのです。
私は積極的に営業を働きかけることは個人的な方針としてやらないのですが、
そのときはさすがにもうひと押し説明をすべきであったのかと悔やみ、ひとことでは言い表せない
屈辱感でがっくりきます。
個人的に説得力や技量が足りないにしても、沖縄の伝統建築美なんてそんな程度にしか
一般的には理解されていないのかと、悲観的な思いにかられてしまいます。
私自身は漆喰の歴史や長所・短所を理解した上で、やはりすぐれた建築材だという
思いがあったのですが、その思いが揺らいできたときに出会ったのが「柳宗悦」の文章でした。
この人の名前は新聞で見聞きして、有名な「文化人」という程度で知っていましたが、
業績はまったく知りませんでした。
「民芸運動の父」とも称される方ですが、業績等は「日本民藝館」のHPを参考にした方がいいでしょう。ここです→ http://www.mingeikan.or.jp/html/yanagi-soetsu.html
柳宗悦は早くから沖縄の工芸品や建築に高い評価を与えていたのでした。
たまたま、何かの本で柳宗悦が沖縄の瓦屋根の家並みを絶賛しているという一文をみつけたので、
あるときその著作をちょっと探してみたのです。
彼の著作『民藝四十年』(岩波書店)の中に『琉球の富』という論考が収められています。
このなかで彼は沖縄の建築、文芸、音楽、舞踊、衣装、工芸(染物、織物、陶器、彫刻)など広範囲に
わたりひとつひとつ丁寧に根拠を示して賞賛の言葉を掲げています。
そのなかの項目に「本葺瓦」という項目があり、いわゆる島瓦(赤瓦)のことをさしているのですが、
彼はそこの文末にこう言っています、「沖縄の都市の美観はその本葺瓦の屋根に集まるのです。
もしこの屋根が無くなったとしたら、沖縄はその美しさの大半を失うでしょう」
悲しいかな私が感じていたことを、彼はすでに70年近くも前に述べているのです。
彼のこの文章は1939年(昭和14年)に書かれたものです。
当時、彼の賞賛した那覇首里の瓦屋根の美観は戦争ですべて灰燼に帰しました。
だからといって、今となっては無意味な言葉でしょうか?私には今現在でも十分に通用する警鐘だと思うのです。
戦争による喪失はうちなーんちゅに責任はありません。
しかし、今のうちなーんちゅには、現役の伝統建築物を生かす、努力・責任があるのではないのでしょうか?
彼はうちなーんちゅ自らの自信をもたない「不必要な卑下」はしない方がいいと助言しています。
しかし、私には一般的な今のうちなーんちゅは、卑下以前の次元で、見た目の華やかさに気をとら
れ、伝統建築に対する美意識が衰えてしまっているようにしか感じられません。
前にも書きましたが、コンリート住宅は強度は強く、見た目にもいろいろと工夫ができるので
今のうちなーんちゅが大好きな建築です。
でもどんなに立派につくってもはたして50年後にはどのていどの住宅が残っているでしょうか?
一般のコンクリート住宅は人間の寿命より短いものです。
一方、木造瓦屋根住宅は大切に使えば100年単位の寿命なのですが、
その寿命を果たす以前にどんどん取り壊されています。
今のうちなーんちゅには天寿をまっとうできなくて取り壊される伝統的木造瓦屋根住宅の
木の叫び、瓦の悲鳴は聞こえていないのです。
「強制退去」扱いの屋敷の神様は、家人達の繁栄のために
とどまっていただけけるのでしょうか?
そういうことも年寄りから忠告されるので形式的には関心は寄せても、
本心からは関心はないのかもしれません。
まあ、当然のことですが一県民の私には出来ることはかぎられていますので、
あんまり悲観的になってもしょうがないです。
最終的には「なんくるないさ」ですか?
立派な木造赤瓦住宅に営業で漆喰塗り替えをお願いに伺うと、「検討する」と返事を頂きます。
しばらくして再訪するとその瓦屋根には既にペンキや防水塗装が施されているのです。
私は積極的に営業を働きかけることは個人的な方針としてやらないのですが、
そのときはさすがにもうひと押し説明をすべきであったのかと悔やみ、ひとことでは言い表せない
屈辱感でがっくりきます。
個人的に説得力や技量が足りないにしても、沖縄の伝統建築美なんてそんな程度にしか
一般的には理解されていないのかと、悲観的な思いにかられてしまいます。
私自身は漆喰の歴史や長所・短所を理解した上で、やはりすぐれた建築材だという
思いがあったのですが、その思いが揺らいできたときに出会ったのが「柳宗悦」の文章でした。
この人の名前は新聞で見聞きして、有名な「文化人」という程度で知っていましたが、
業績はまったく知りませんでした。
「民芸運動の父」とも称される方ですが、業績等は「日本民藝館」のHPを参考にした方がいいでしょう。ここです→ http://www.mingeikan.or.jp/html/yanagi-soetsu.html
柳宗悦は早くから沖縄の工芸品や建築に高い評価を与えていたのでした。
たまたま、何かの本で柳宗悦が沖縄の瓦屋根の家並みを絶賛しているという一文をみつけたので、
あるときその著作をちょっと探してみたのです。
彼の著作『民藝四十年』(岩波書店)の中に『琉球の富』という論考が収められています。
このなかで彼は沖縄の建築、文芸、音楽、舞踊、衣装、工芸(染物、織物、陶器、彫刻)など広範囲に
わたりひとつひとつ丁寧に根拠を示して賞賛の言葉を掲げています。
そのなかの項目に「本葺瓦」という項目があり、いわゆる島瓦(赤瓦)のことをさしているのですが、
彼はそこの文末にこう言っています、「沖縄の都市の美観はその本葺瓦の屋根に集まるのです。
もしこの屋根が無くなったとしたら、沖縄はその美しさの大半を失うでしょう」
悲しいかな私が感じていたことを、彼はすでに70年近くも前に述べているのです。
彼のこの文章は1939年(昭和14年)に書かれたものです。
当時、彼の賞賛した那覇首里の瓦屋根の美観は戦争ですべて灰燼に帰しました。
だからといって、今となっては無意味な言葉でしょうか?私には今現在でも十分に通用する警鐘だと思うのです。
戦争による喪失はうちなーんちゅに責任はありません。
しかし、今のうちなーんちゅには、現役の伝統建築物を生かす、努力・責任があるのではないのでしょうか?
彼はうちなーんちゅ自らの自信をもたない「不必要な卑下」はしない方がいいと助言しています。
しかし、私には一般的な今のうちなーんちゅは、卑下以前の次元で、見た目の華やかさに気をとら
れ、伝統建築に対する美意識が衰えてしまっているようにしか感じられません。
前にも書きましたが、コンリート住宅は強度は強く、見た目にもいろいろと工夫ができるので
今のうちなーんちゅが大好きな建築です。
でもどんなに立派につくってもはたして50年後にはどのていどの住宅が残っているでしょうか?
一般のコンクリート住宅は人間の寿命より短いものです。
一方、木造瓦屋根住宅は大切に使えば100年単位の寿命なのですが、
その寿命を果たす以前にどんどん取り壊されています。
今のうちなーんちゅには天寿をまっとうできなくて取り壊される伝統的木造瓦屋根住宅の
木の叫び、瓦の悲鳴は聞こえていないのです。
「強制退去」扱いの屋敷の神様は、家人達の繁栄のために
とどまっていただけけるのでしょうか?
そういうことも年寄りから忠告されるので形式的には関心は寄せても、
本心からは関心はないのかもしれません。
まあ、当然のことですが一県民の私には出来ることはかぎられていますので、
あんまり悲観的になってもしょうがないです。
最終的には「なんくるないさ」ですか?
Posted by 瓦屋根 at 14:52│Comments(2)
│文化
この記事へのコメント
「なんくるないさ」ではいけないですよね
県民一人一人が足下にある美しいもの、大切な物を
きちんと見る目を養っていって、大事に残していかないといけない
瓦屋根さんのように一人一人が考えないといけないですよね
目先の物に流されず、本物を見極める目を養っていきたいと思います。
今日も勉強になりました。
ありがとうございます。
県民一人一人が足下にある美しいもの、大切な物を
きちんと見る目を養っていって、大事に残していかないといけない
瓦屋根さんのように一人一人が考えないといけないですよね
目先の物に流されず、本物を見極める目を養っていきたいと思います。
今日も勉強になりました。
ありがとうございます。
Posted by kenp at 2006年02月01日 17:27
kenpさん、またまたコメントありがとうございます。
那覇のあるところに、沖縄には少し珍しい入母屋作りの大きな木造セメント瓦住宅がありましたが、こないだ通り過ぎたときに更地になっていました。がちょーん!壊される直前であれば写真撮りたかったです。
那覇のあるところに、沖縄には少し珍しい入母屋作りの大きな木造セメント瓦住宅がありましたが、こないだ通り過ぎたときに更地になっていました。がちょーん!壊される直前であれば写真撮りたかったです。
Posted by 瓦屋根 at 2006年02月03日 20:26