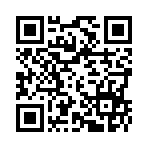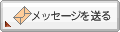2005年12月09日
いまさらですが、漆喰って?
漆喰赤瓦屋根木造住宅(具志頭村:築50年余)

漆喰(しっくい)ってどんなもの?→語源は石灰(せっかい)
年配の方なら成分など知らなくても物を見てすぐにわかるのですが、20代~40代の方々では現物を触ったことも見たこともないなんて方が多いです。今は小学生のほうがよく知っています。学校の図工などで、漆喰シーサーを造るので知っているようです。
沖縄の漆喰は方言では「ムチ」と呼ばれています。お仕事探索(営業)のときに「瓦屋根のムチを塗り替えます」といっても、「餅(もち)はいりません」といわれてがっくりくるときがあります。
さて本題に戻りますが、漆喰は石灰を原料に、のり剤(つなぎのような役割)として、わらや海草などが練り込まれたものです。地域によってのり剤は変わるようです。沖縄では稲わらが混ぜ込まれています。本土では主に壁に使われ、沖縄では瓦屋根の仕上げに使われています。
もうすこし細かくいいますと、石灰(生石灰:酸化カルシウム)に水を加えますと、化学反応を起こし発熱しペースト状の消石灰(水酸化カルシウム)になりますが、これにのり剤を加えたのが漆喰になるわけです。この漆喰を壁や屋根に塗りつけ仕上げると、炭酸ガスを吸いながら乾燥・硬化していきます。乾いてカチカチの石化した状態は炭酸カルシウムとなっています。いわゆる石灰岩ですね。つまり漆喰塗りが乾いて完成したら、成分は石灰の原材料である石灰岩に戻っているのです。
漆喰の歴史→五千年の歴史
漆喰は五千年の歴史を持ち、エジプトのピラミッド、古代ローマの都、万里の長城でも使われているそうです。
もちろん現在でも世界中で建築物に使われています。ヨーロッパの有名な教会などの壁画芸術であるフレスコ画の下地は漆喰です。
日本本土では城づくりが盛んになるとともに工法も発展し、今日まで日本独自の建築文化を支えています。
沖縄では14世紀に瓦が伝わって以降、台風や厳しい暑さに耐えるため独自の工法が発展しました。瓦が台風などで吹き飛ばされないように瓦のつなぎ目を漆喰でつなぐのですが、これが独特の美しい景観を発達させました。
漆喰の特徴→天然素材で無公害
1.漆喰の原材料は石灰岩や稲わらなどの天然素材なので無公害です。
2.漆喰壁では防カビ・防結露・防火等の役割を果たしています。本土の歴史的木造建築物(文化財)が長持ちするのは、漆喰壁の役割も大きいといわれています。
沖縄の漆喰→世界中の知恵が結集
1.沖縄の漆喰は、石灰にわらが練りこまれています。
2.漆喰の使用: 漆喰は屋根瓦の継ぎ目および棟筋に塗りつけます。
その主な理由は、台風で瓦が吹き飛ばされないように押さえつけることと、雨の吹き込み防止です。 しかしその理由とは別に美しい独特の景観を作り出しました。
3.漆喰の利点→昔から瓦は割れたり劣化しないかぎり、リサイクルされてきました。漆喰は瓦を傷めたり、劣化させたりしません。何度でも塗り替えができます。
漆喰は適度な硬さと柔軟性をもち、また断熱効果もあるため、木造瓦屋根に適していました。
4.沖縄の漆喰瓦屋根は世界の知恵が結集
ある著名な建築家が、西洋の建築は「壁の文化」といい、日本の建築は「屋根の文化」といったそうです。おおげさですがこの「屋根の文化」に漆喰を巧みに取り入れた沖縄の漆喰瓦屋根は世界中の知恵が結集した建築文化といえるのです。
でも、残念ながらどんどん取り壊されたりしてこの景観も一部の地域のみに残るものとなってきました。

漆喰(しっくい)ってどんなもの?→語源は石灰(せっかい)
年配の方なら成分など知らなくても物を見てすぐにわかるのですが、20代~40代の方々では現物を触ったことも見たこともないなんて方が多いです。今は小学生のほうがよく知っています。学校の図工などで、漆喰シーサーを造るので知っているようです。
沖縄の漆喰は方言では「ムチ」と呼ばれています。お仕事探索(営業)のときに「瓦屋根のムチを塗り替えます」といっても、「餅(もち)はいりません」といわれてがっくりくるときがあります。
さて本題に戻りますが、漆喰は石灰を原料に、のり剤(つなぎのような役割)として、わらや海草などが練り込まれたものです。地域によってのり剤は変わるようです。沖縄では稲わらが混ぜ込まれています。本土では主に壁に使われ、沖縄では瓦屋根の仕上げに使われています。
もうすこし細かくいいますと、石灰(生石灰:酸化カルシウム)に水を加えますと、化学反応を起こし発熱しペースト状の消石灰(水酸化カルシウム)になりますが、これにのり剤を加えたのが漆喰になるわけです。この漆喰を壁や屋根に塗りつけ仕上げると、炭酸ガスを吸いながら乾燥・硬化していきます。乾いてカチカチの石化した状態は炭酸カルシウムとなっています。いわゆる石灰岩ですね。つまり漆喰塗りが乾いて完成したら、成分は石灰の原材料である石灰岩に戻っているのです。
漆喰の歴史→五千年の歴史
漆喰は五千年の歴史を持ち、エジプトのピラミッド、古代ローマの都、万里の長城でも使われているそうです。
もちろん現在でも世界中で建築物に使われています。ヨーロッパの有名な教会などの壁画芸術であるフレスコ画の下地は漆喰です。
日本本土では城づくりが盛んになるとともに工法も発展し、今日まで日本独自の建築文化を支えています。
沖縄では14世紀に瓦が伝わって以降、台風や厳しい暑さに耐えるため独自の工法が発展しました。瓦が台風などで吹き飛ばされないように瓦のつなぎ目を漆喰でつなぐのですが、これが独特の美しい景観を発達させました。
漆喰の特徴→天然素材で無公害
1.漆喰の原材料は石灰岩や稲わらなどの天然素材なので無公害です。
2.漆喰壁では防カビ・防結露・防火等の役割を果たしています。本土の歴史的木造建築物(文化財)が長持ちするのは、漆喰壁の役割も大きいといわれています。
沖縄の漆喰→世界中の知恵が結集
1.沖縄の漆喰は、石灰にわらが練りこまれています。
2.漆喰の使用: 漆喰は屋根瓦の継ぎ目および棟筋に塗りつけます。
その主な理由は、台風で瓦が吹き飛ばされないように押さえつけることと、雨の吹き込み防止です。 しかしその理由とは別に美しい独特の景観を作り出しました。
3.漆喰の利点→昔から瓦は割れたり劣化しないかぎり、リサイクルされてきました。漆喰は瓦を傷めたり、劣化させたりしません。何度でも塗り替えができます。
漆喰は適度な硬さと柔軟性をもち、また断熱効果もあるため、木造瓦屋根に適していました。
4.沖縄の漆喰瓦屋根は世界の知恵が結集
ある著名な建築家が、西洋の建築は「壁の文化」といい、日本の建築は「屋根の文化」といったそうです。おおげさですがこの「屋根の文化」に漆喰を巧みに取り入れた沖縄の漆喰瓦屋根は世界中の知恵が結集した建築文化といえるのです。
でも、残念ながらどんどん取り壊されたりしてこの景観も一部の地域のみに残るものとなってきました。
Posted by 瓦屋根 at 22:01│Comments(0)
│伝統建築